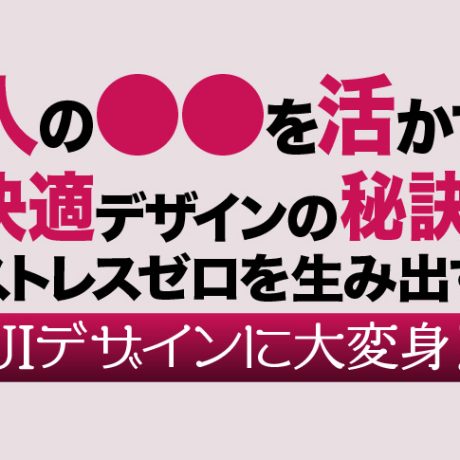記事目次
日常的なさまざまな製品において、便利さを追求し効率性を上げる機能を盛り込むことが多い。
しかし、こうした便利機能というのは、わかってる人や慣れている人には便利で快適であっても、それを使いこなせない人にとってはストレスの元になっていることに、作り手側はなかなか気づきません。
今回は、プラス面の機能を盛り込むことより、マイナス面の間違いやわかりにくい要因を無くすことが、これからの「ユーザビリティが目指すトレンド」ということを解説します。
便利さと分かりにくさは紙一重

全国で導入されている高速道路の料金精算機に潜む非ユーザビリティ性能。あなたは、料金所を通過するその瞬間、このマシーンの使い方を理解できますか?
答えは最後に↓
ユーザビリティの定義が示す「わかりやすい」ということ
ユーザビリティの意味や定義を端的に示すものとして、もっとも一般的なのが、国際規格となっている「ISO9241-11」です。
また、ユーザビリティの権威であるアメリカのヤコブ・ニールセン博士が、1994年「ユーザビリティエンジニアリング原論(邦訳1999年)」の中で謳われている「ユーザビリティの5つの定義」など、わかりにくいユーザビリティを一般化するための基準が設けられています。
主観的な判断によるところが大きいユーザビリティは、読み解く人の価値観の違いにより、賛否が分かれるところです。

国際規格「ISO9241-11」で示されているユーザビリティは、
[効果]
ユーザーがサイトを利用する際に、誤解したり間違ったりせずに、目的を達成できるか?
[効率]
ユーザーが目的の情報を探す際に、不必要に時間を要したり、遠回りな遷移をせずに、最短距離と最短時間で、目的を達成できたか?
[満足度]
ユーザーがサイトを閲覧する中で、表示速度の遅さや、説明が不十分であったりわかりにくいためにストレスを感じて、満足度を下げていないか?
というように、「効果」「効率」「満足度」の3つの観点からユーザビリティの性能を評価できることが特徴です。
ヤコブ・ニールセンの「ユーザビリティの5つの定義」
さらに、この定義にヤコブ・ニールセンの「ユーザビリティの5つの定義」を重ね合わせて考えて行くと、比較的ユーザビリティ性能を具体的に理解するヒントが見えてきます。

学習しやすさ(Learnability):
初めてサイトを利用する際であっても、ユーザーが直感的に使い始められるよう、簡単に学習できるようにしなければならない
という意識があって、初めて「効果」や「効率」を高めるスタートに立てると思います。
記憶しやすさ(Memorability):
初めてのユーザや、しばらく使っていなかった場合でも、簡単に覚えられて、すぐに使えはじめられなければならない
という、記憶のしやすさと明快なわかりやすさが、間違いにくいサイトとしての「効果」を産み出すと思います。
効率性(Efficiency):
ユーザーはサイト内の仕組みを一度学習すれば、高い生産性を上げられるように、効率的に使い続けられなければならない
という、ショートカットボタンなどのように、効率的で覚えやすいインタフェースによって「効率性」が高まっていくのだと思います。
エラー(Errors):
ユーザーが間違いや誤解が起きにくいこと、もし間違った操作やエラーが発生した場合でも、致命的な状況にならず、容易に正しい状態へ回復できなければならない
という、問題を回避できる明解な説明や使い勝手によって、ユーザーが問題から離脱できる「わかりやすさ」や「効率性」が実現されると思います。
主観的満足度(Satisfaction):
ユーザーの趣味・嗜好に寄り添い、ユーザーが主観的に満足できるような楽しく快適に利用できなければならない
という、ターゲットとする利用ユーザーのコンテンツ体験において、ユーザー自身の評価として満足できる「質」が、提供されていることだと思います。
ユーザビリティの定義とUI/UXの関係
我々が日常的に意識しているUI/UXは、このユーザビリティの定義でいうと、
不備を少なくするためには「UI」性能を吟味することが必要であり、
効率性を高めるためには「UX」を実現していくことが必要
と考える事ができます。

家電リモコンにみる効率化の功罪
機能性と効率性を高めていくことは、製品のプラス面を最大化する家電リモコンに代表される「いわゆる全部入り」の流行を呼ぶことになりました。
しかし、わかっている人には便利なユーティリティ性能は、それを必要としないユーザーやITリテラシーに乏しい人にとっては、返ってわかりにくさが強まることで、逆に効率性が下がってしまうという皮肉な事態を招くことになりました。

マイナス要素を無くすことが、昨今のユーザビリティのトレンド
家電リモコンにみるような単純化と同様に、リーマンショック以降のWEBサイトの表現においても、「わかりにくいこと」や「使いにくいこと」につながるマイナス面をいかに小さくしていくかを問う、UIデザインがより一層重要視されるトレンドを産み出したと言えます。

すべてのユーザーが同じようにわかっているわけではない
さて、そんなワケで、冒頭に紹介した高速道路の自動精算機は、一つ一つは機能性の高い仕組みであるものの、プラス面ばかりが着目された結果、操作手順と合致しにくい配置やカラーリングは直感性に欠けるためわかりにくく、マイナス面が増大してしまうという皮肉な結果になってしまった例と言えましょう。
要は、利用するユーザーがすべて同じように「高いリテラシー」や「理解力」を持ち合わせているワケではないということを、しっかりと意識することが大切だということなのです。

▼通常の支払い
①通行券を挿入
②画面に表示される通行料を確認
③硬貨で支払う場合投入
④紙幣で支払う場合挿入
⑤クレジットカードやETCカードで支払う場合挿入
⑥硬貨のおつりを受け取る
⑦紙幣のおつりを受け取る
⑧領収書が必要な場合はボタンを押す
⑨領収書を受け取る▼障がい者割引制度を利用する場合
㋐レバーを下げて係員を呼び出す
㋑カメラに向かって障害者手帳をかざす
その後、通常の支払い手順
![よくわかるUIデザイン講座 [ continue.jp ] よくわかるUIデザイン講座 [ continue.jp ]](https://continue.jp/wp-content/uploads/2022/11/rogoset.png?1768365554)