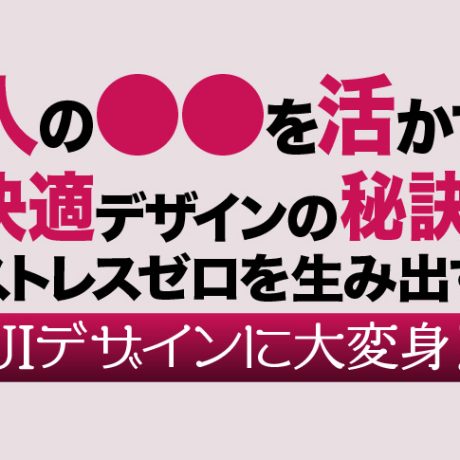記事目次
同じ特徴を持つ要素同士は離れていても、
関係性が深いグループとして認識される。
人は、色や形・サイズ・方向などの視覚的に共通の特徴をもつもの同士は、共通性がないものよりも「関係性が深いもの」として認識する習性があり、プレグナンツの法則(ゲシュタルト原理)の中でも、もっとも重要な法則のひとつ。
同じ特徴の要素同士である場合、位置が離れていたり、分散していても同じグループとして認識されるため、近接の法則や閉合の法則とは異なる特性を持つ。
特に、同じ色を採用することで、形など他の特徴よりも強く認知できるため、異なる形や大きさの要素を同じグループとして認知できる。
ちなみに、同じ要素としてグループ化されている周囲のものから孤立した要素は目立ちやすく無意識のうちに着目される。

表現可能なデザインパーツ
具体例
-
スポーツの試合で各チームが着用しているユニフォーム
-
チラシ広告などでセール品だけを大きく扱うことで、通常商品とは違うグループであることを印象づける
-
同じ色を使用したリンクテキストや、同じボタン形状で示されたCall to Actionボタン
提唱者・発祥エピソード
ゲシュタルト心理学の創設者の一人であるチェコの心理学者マックス・ヴェルトハイマー氏によって、1923年「ゲシュタルト原則」の基礎となる6原則(近接・類同・連続・閉合・共通運命・良い形)が発表された。
参考文献・参考サイト
ビジュアルデザインにおける類同の法則
ニールセン博士のAlertbox
類同(ゲシュタルト原則)
UX TIMES
https://uxdaystokyo.com/articles/glossary/similarity/
![よくわかるUIデザイン講座 [ continue.jp ] よくわかるUIデザイン講座 [ continue.jp ]](https://continue.jp/wp-content/uploads/2022/11/rogoset.png?1752284168)