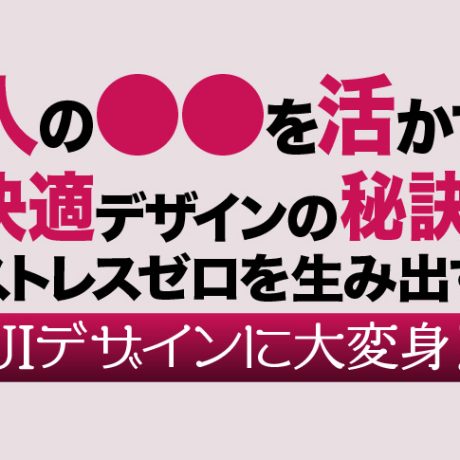人は無意識のうちに自らの発言や、 人は自身の信念、行動や態度を決定したり宣言した際、決定した事を完遂したり保持し続けたいという心理が働く。
人から何かを依頼されて自ら能動的に関わり合いを持った際や、周囲から注目されている立場にある時は、特に働きやすい。
ちなみに、決定した決意を再選択したり、再び議論するなどの度重なる判断機会を減らして、意志決定をパターン化することによって、ストレスを軽減できる効果がある。
具体例
周りの人に「禁煙」や「ダイエット」など、宣言してしまったことを続けようとする
欲しい商品があってお店に行ったが品切れだったが、せっかく来たのでなんか買って帰ろうと思う
気に入ったものはずっと使い続けたいため、買い替えたり関連商品を購入する
提唱者・発祥エピソード アリゾナ州立大学の心理学およびマーケティングの教授ロバート・B・チャルディーニ氏が、1984年、『Influence: The Psychology of Persuasion(影響力の武器:なぜ、人は動かされるのか)』という著書の中で示された、人の行動を変えてしまう影響力を持つ6つの項目の一つとして提唱された。
参考文献・参考サイト
無意識に行動に表れている「一貫性の法則」を解説https://ferret-plus.com/4756
ferret
一貫性の原理https://uxdaystokyo.com/articles/glossary/principleofconsistency/
UX TIMES
一貫性の原理とは|人間心理・マーケティング、ビジネス、交渉に役立つテクニックhttps://lab.kutikomi.com/news/2020/12/17/ikkannsei/
口コミラボ
一貫性の原理https://ja.wikipedia.org/wiki/一貫性の原理
ウィキペディア
関連タグ アンダードッグ効果 , タイトル@表現可能なデザインパーツ , チャルディーニの法則 , ツァイガルニク効果 , ディドロ効果 , ナビゲーション@表現可能なデザインパーツ , ビジュアル@表現可能なデザインパーツ , フットインザドア , リンク/ボタン@表現可能なデザインパーツ , 一貫性 , 動機 , 行動過程 , 返報性の原理 , 関連リンク@表現可能なデザインパーツ
このページと関係がある認知科学用語
チャルディーニの法則 科学的根拠を示す研究結果や、具体的な事例を交えて、心理学の視点から解説された、交渉相手を心理的に変化させて交渉を有利にする説得術を示す6項目。 交渉する側からすると、人間心理を巧みに利用して相手から好感を得られることで、利益…
ツァイガルニク効果(ザイガルニック効果) 人は目標を達成し完了した事柄よりも、目標を達成できず、途中で中断してしまった事柄の方をよく覚えており、「続きを早く再開したい」とか「最後まで終わらせたい」など、続きが気になってしまう現象。 しかし、自分にとってどうでもいいよ…
返報性の原理 人は相手から、好意や譲歩、恩義など、何かを受け取ったことに対して、「お返しをしたい」と自然に感じてしまう心理作用。 返報性には、相手の好意や親切に対して、同じような気持ちをお返ししようとするポジティブな心理作用だけでなく、仕…
フットインザドア(段階的要請法) 新規のセールスや難易度の高い交渉や要求を成功させる交渉術として、本題の要求を提示する前に、簡単で容易に承諾されそうなことから提示し、段階的に条件を膨らませて要求レベルを上げていく方法。 訪問販売員が粘る際に、閉めかけたドアに…
アンダードッグ効果(判官贔屓〈ほうがんびいき〉) 不利で弱い立場にありながらも、精一杯努力し強者に立ち向かう姿に同情し、応援したくなる心理効果で、人は元々、集団生活の中で立場が弱い者を守ろうとする本能が働き、事前に不利であることが周知されるアナウンス効果によって起きる。 な…
ディドロ効果 今まで知る機会がなかった新しい価値観に出会った際、それまでの生活環境を新しい価値に合わせた雰囲気や様式に統一したくなる消費を拡大する心理効果。 人は、本能として一貫性を求める傾向があるため、自身が気に入った環境を損なうことに…

![よくわかるUIデザイン講座 [ continue.jp ] よくわかるUIデザイン講座 [ continue.jp ]](https://continue.jp/wp-content/uploads/2022/11/rogoset.png?1752306648)