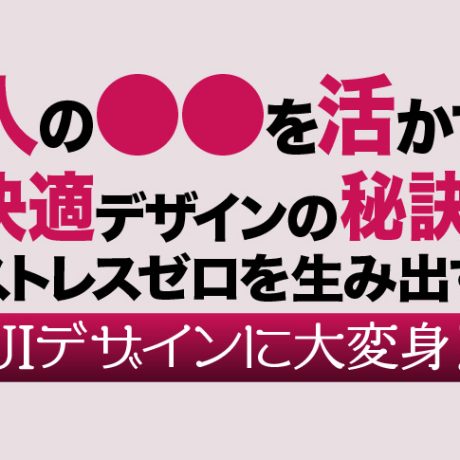記事目次
囲まれた情報をグループとして認識したり、
欠けている情報を脳内で復元できる。
人は、〈 〉や[ ]、破線のような何かで括られた情報は、ひとつの矩形として補完されるため、囲まれた情報は一つのグループとして認識される。
また、すでに理解や認識している情報やオブジェクトについて、一部が欠けていたり隠れている状態でも、不足している部分や見えない部分を脳内で補完し、分断されている状態や欠けている状態から、完全な状態に復元したり、全体像を把握しようとする意識が自動的に行われる。
ちなみに、この考え方から、異なる情報や異なる体裁の情報を矩形など閉じたエリアに格納することで、一つのグループとして認識され、その矩形の全体が見えない欠けた状態でも完全な形を想像できることを利用し、水平スクロールのメニュー表示に活用されている。

表現可能なデザインパーツ
具体例
-
(*^_^*)などのいわゆる「顔文字」は、文字情報の羅列が一つの顔として認識される。
-
写真・文字・アイコンなど異なるパーツを組み合わせた情報も、矩形の中に収めることで一つのメニュー情報として認識される。
- ロゴマークやロゴタイプでは、情報の一部が欠けたり隠し絵のように扱うことで、記憶に残る強い印象を演出。

提唱者・発祥エピソード
ゲシュタルト心理学の創設者の一人であるチェコの心理学者マックス・ヴェルトハイマー氏によって、1923年「ゲシュタルト原則」の基礎となる6原則(近接・類同・連続・閉合・共通運命・良い形)が発表された。
参考文献・参考サイト
コトバンク
閉合(ゲシュタルト原則)
UX TIMES
https://uxdaystokyo.com/articles/glossary/closure-gestalt-principles/
『マンガ学』の「閉合」法則による ジャンプ連載作品のコマ間移行分析
Balloon Inc.
https://lloon.jp/manga-jump/
ビジュアルデザインにおける閉合の法則
ニールセン博士のAlertBox
https://u-site.jp/alertbox/principle-closure
![よくわかるUIデザイン講座 [ continue.jp ] よくわかるUIデザイン講座 [ continue.jp ]](https://continue.jp/wp-content/uploads/2022/11/rogoset.png?1752306142)