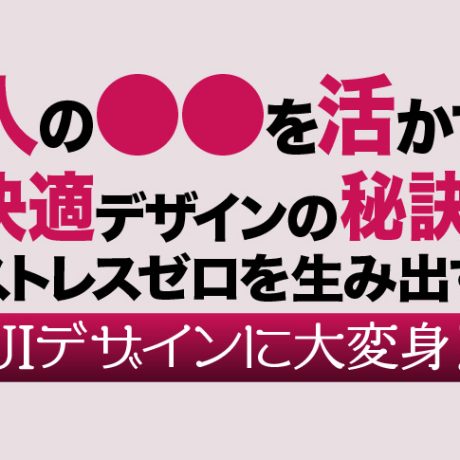記事目次
事前に得た情報によって、
その後の行動に対して無意識に影響を与える。
あらかじめ見聞きした刺激情報(文字・画像・動画・音楽など)によって、その後の課題や行動によって処理される刺激情報が、無意識のうちに促進や抑制などの影響を受ける連想能力による効果。
先行する刺激をプライマー、後に影響を受ける後続する刺激をターゲットと言い、プライミング効果には、直接的プライミングと間接的プライミングがある。
直接プライミング効果とは
プライマーとターゲットとで同じ刺激が繰り返されることで、反復プライミング効果とも呼ばれる。
通常は知覚レベルで観察される現象で、例えば「プ○○○○グ効果」の○部分を埋める際に、この効果を連想できる。
間接プライミング効果とは
プライマーとターゲットとが異なる場合に起きる効果で、例えば「○ープ」という文字列の○を埋める際に、事前に得た情報(プライマー)が食べものに関するものなら「スープ」、シャワー関するものなら「ソープ」を連想し、意味的関係によって連想されることを意味的プライミングとも呼ぶ。
ちなみに、人間は膨大な情報を記憶として蓄えているが、各記憶は取り出しやすいように、関連する情報同士はネットワーク状に構成されている。
ある情報がチョイスされた際、その情報と関係性のある情報は、取り出しやすい状態となり、結び付きの深い情報は活性化して次々と情報処理されやすくなるため、無意識の中で直感的に働くシステム1と呼ばれる処理方法によって、連想処理されていく。

表現可能なデザインパーツ
具体例
- 年間の売り上げ目標を書き記したり口に出して発表すると、目標を達成するための行動を意識する。
- テレビでドラマを観ていて、お菓子のCMが気になって、急にそのお菓子が食べたくなる。
- 何となく訪れた自動車のサイトで、購入時期に関するアンケート調査をみて、車購入の意識が高まり、実際に購入を検討したくなる。
提唱者・発祥エピソード
1970年代初頭、アメリカの心理学者デイビット・G・メイヤー氏と、ロガー・W・シュヴァネヴェルト氏は、被験者にある文字列を見せる前に、それに似た意味を持つ単語を事前に見せておくと、その文字列をより早く認識するという実験において、人間の連想能力を導き出した。
参考文献・参考サイト
脳科学辞典
プライミング効果
UX TIMES
https://uxdaystokyo.com/articles/glossary/primingeffect/
プライミング効果の意味とは? 仕事・勉強に応用する方法3つ
STUDY HACKER
https://studyhacker.net/priming-effect
プライミング効果
心理学用語集サイコタム
https://psychoterm.jp/basic/cognition/priming-effect
プライミング効果〜無意識に買ってしまう心理学とは
マケフリ
https://makefri.jp/marketing/6371/
プライミング効果
科学事典
https://kagaku-jiten.com/social-psychology/individual/priming-effect.html
![よくわかるUIデザイン講座 [ continue.jp ] よくわかるUIデザイン講座 [ continue.jp ]](https://continue.jp/wp-content/uploads/2022/11/rogoset.png?1752608035)