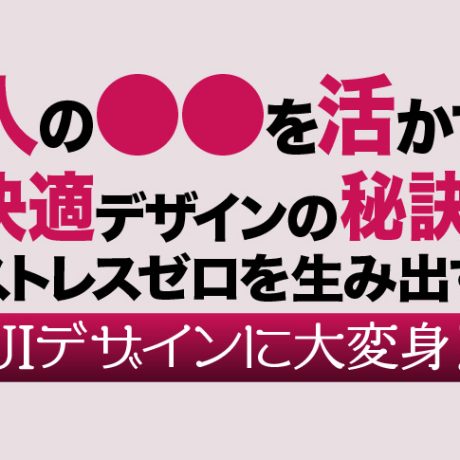記事目次
最初に提示された数字が意識に固定化され、
以降の数字に対する判断が左右される。
人は、適切な判断ができるだけの情報量がない状況下で、限られた情報だけで判断しなければいけない時、特に最初に提示された数字に対して強い印象を受けて、船が碇を降ろして固定するかのように、無意識のうちにその数字に思考が固定化してしまう。
そもそも人は、同時に2つ以上の情報を処理することができないために、特定の情報以外を排除して、ひとつのモノゴトに集中してしまうという「焦点化の法則」が働きやすい。
そこで、本人の意志に関わらずアンカーとなった最初の情報が前提条件となって、以降に提示される数字との比較において、優劣、損得などの判断がそれに左右される現象で、心理学の「認知バイアス」のひとつ。
ちなみに、最初に提示される情報が意味情報の場合は、数字よりもアンカリング効果は低い。
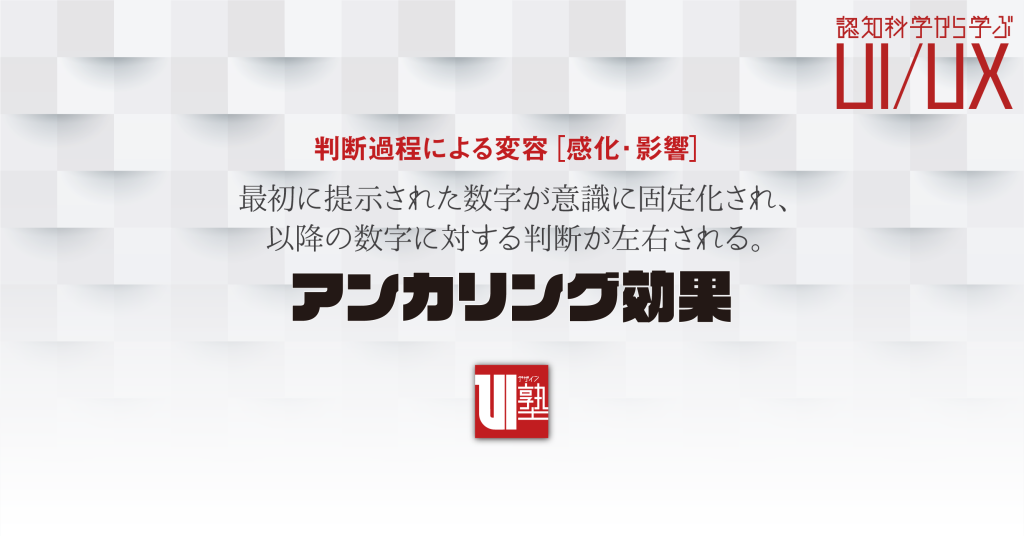
表現可能なデザインパーツ
具体例
-
通常の価格に縛られて、値下げ後の価格が魅力的に感じる
-
待ち合わせの時間に30分遅れると連絡したが、実際は10分遅れで到着したことに、遅れたことに変わらないが早く着いたと感じられる
-
目標となる数値を先に示した上で、○%アップ、○%達成などと効果をアピール
提唱者・発祥エピソード
2002年にノーベル経済学賞を受賞した米国の行動経済学者ダニエル・カーネマン氏と、米国の心理学者エイモス・トヴェルトスキー氏が、1974年『サイエンス誌』で発表した論文「先行する何らかの要素(アンカー)によって物事の判断が左右される『認知バイアス』の1つ」の中で紹介されたことで、「すぐできる効果的なマーケティング手法」として瞬く間に世の中に広がる。
参考文献・参考サイト
【アンカリング効果とは】最初の数字が人の行動を決める!? 活用法と注意点
マイナビエージェント
https://mynavi-agent.jp/dainishinsotsu/canvas/2021/12/post-611.html
アンカリング効果
UX TIMES
https://uxdaystokyo.com/articles/glossary/anchoringeffect/
アンカリング効果の意味やマーケティングとの関係について解説
LeadPlus
https://www.leadplus.co.jp/inbound/blog/anchoring-effect-and-marketing.html
アンカリング効果とは?マーケティングで使えるユーザー心理を掴むコツ
ferret
https://ferret-one.com/blog/anchoring-effect
![よくわかるUIデザイン講座 [ continue.jp ] よくわかるUIデザイン講座 [ continue.jp ]](https://continue.jp/wp-content/uploads/2022/11/rogoset.png?1752522802)