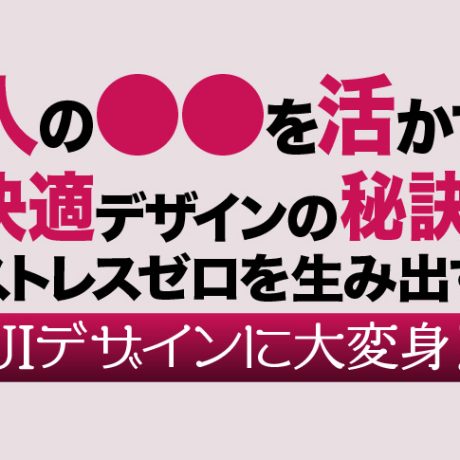記事目次
今回は、サイトを利用するすべてのユーザーの中でも、特に新規ユーザーに対して、わかりやすく行きたい情報へ直感的に遷移可能で、機動的な行動をサポートできるデザイン表現について、認知科学で考えてみたいと思います。
関心の高い項目からメニューを並べることで
利用を喚起するBeforeとAfter
情報を発信する側だけの理由で、情報を整理し階層化してサイト構造を構築してしまうと、ユーザーの直感的な操作が制限される「目次化」されたグローバルナビゲーションになりやすい。
そのため、
●サイトにとって重要視するユーザー層はだれなのか、
●一番興味関心が高い情報は何なのか?
など、ターゲットユーザーのサイト内行動を想定せずに、情報を発信する側の思惑だけで無意識に並べてしまうグローバルナビゲーションでは、ユーザーの行きたい場所がわかりにくくたどり着けなかったり、ブランドイメージが曖昧になってしまうなどの原因となる。


最初と最後に関心の高いメニューを
配置すると記憶に残りやすい!
グローバルナビゲーションで表示されるメニュー数は、人の短期記憶と密接に関係しているため、多く表示したり構造が複雑になるほど、サイトの全体像を把握できなくなる。
そもそもナビゲーションメニューは左上から利用される傾向が強いことや、興味・関心が強い情報を優先して閲覧するため、グローバルナビゲーションの最初のメニューは記憶に残りやすく、中間にあるメニューは記憶に残りにくい。
また最後のメニューは、短期記憶に保持されやすいため、ユーザーとのコミュニケーションとなる「よくある質問」や「お問い合わせ」への誘導がしやすく、よりロイヤリティ意識の高いコアユーザー向けのコンテンツに対しての関心が強くなる。


わかりやすい遷移導線を実現する
グローバルナビゲーションの認知心理


![よくわかるUIデザイン講座 [ continue.jp ] よくわかるUIデザイン講座 [ continue.jp ]](https://continue.jp/wp-content/uploads/2022/11/rogoset.png?1763700326)