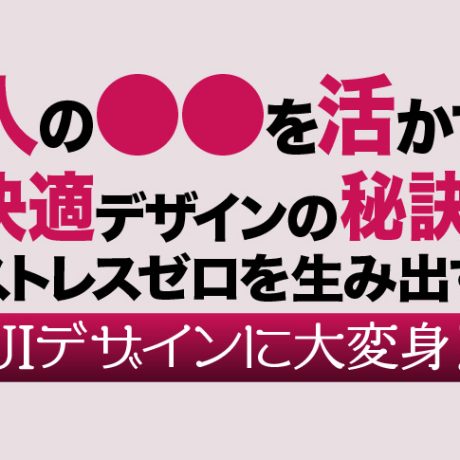人の認知性能に基づく「O次表現」による機能の最大化
人は1秒間にわずかな情報量しか保持できないために、本能的に持つ習性や記憶に刻まれた経験から目の前の情報を瞬時に判断したり、熟考して判断している。 こうした認知性能に基づく人の行動パターンから、予測することで、情報発信や情報認知を適切なタイミングや必要な情報の共有を円滑に行う事ができるんです。 単なるデコレーションとしての装飾デザインに、こうしたエビデンスを合わせもつことで、UIデザインがもっと機能的にすることができます!
#使いやすい
#わかりやすい
#UIデザイン
▼出典・引用
『SUBARUテクノロジームービー【0次安全】』
https://www.youtube.com/watch?v=yJLA7HwY6KE
SUBARUのクルマづくり「テクノロジー:SAFETY 0次安全」 https://www.subaru.jp/brand/technology/technology/safety_primary.html
このページと関係がある認知科学用語
-
再生記憶と再認記憶脳に保持されている顕在記憶やエピソード記憶を、適切なタイミングで思い出す(情報を取り出す)際に、保持されている情報を直接思い出すことを「再生記憶」、提示された情報をきっかけに思い出すことを「再認記憶」という。 一般に再生記憶…
-
短期記憶に関するミラーの法則(マジカルナンバー)数字や単語を記憶する場合、一般的な人の短期記憶(ワーキングメモリ)が保持できる15秒から30秒の間に、正しく覚えられる情報の量(チャンク)は7±2という法則。 チャンクとは、ひとつの意味や認識のかたまりを指し、記憶の限界数を…
-
記憶の多重貯蔵モデル記憶は、役割や機能の違いにより、視覚・聴覚などの五感から受けとる感覚記憶、情報を保管するだけでなく分析・処理する短期記憶、記憶と忘却の反復を経て数十年の単位で貯蔵される長期記憶と、3つの段階で構成されることで、人は非常に多く…
-
2つの思考モード(二重過程理論)人の脳は情報を処理する際、直感や経験則に基づいて無意識に判断する「システム1(速い思考)」と、理性が制御し、直感では処理できない情報を熟考して判断する「システム2(遅い思考)」の2つのモードを使い分けて、脳が受ける負荷を最小…
-
アフォーダンス人をはじめとするあらゆる動物が視覚などの五感から得られた、環境やモノの材質・状態など、さまざまな関係情報から「対象との関係性がどのような状態にあるか」という客観的な事実に基づく意味や価値。 基本的にすべての環境に潜在している…
-
シグニファイア(知覚されたアフォーダンス)事前に使い方を説明しなくても、デザイン的な性能として形や表現方法などの特徴から、「モノや機能がどのように扱われるべきか」という知覚から得られた「手がかり」を、直感的でわかりやすく表現されたシグナルとなるデザイン的な情報。 多…
-
ワーキングメモリ感覚記憶から受けとった音声化できる情報は「音韻ループ」に、ビジュアルイメージは「視空間スケッチパッド」に一時的に保持し、長期記憶から「エピソードバッファ」に読み出された過去の経験や知識を「中央実行系」で解析・処理し、人が行動…
![よくわかるUIデザイン講座 [ continue.jp ] よくわかるUIデザイン講座 [ continue.jp ]](https://continue.jp/wp-content/uploads/2022/11/rogoset.png?1768417665)