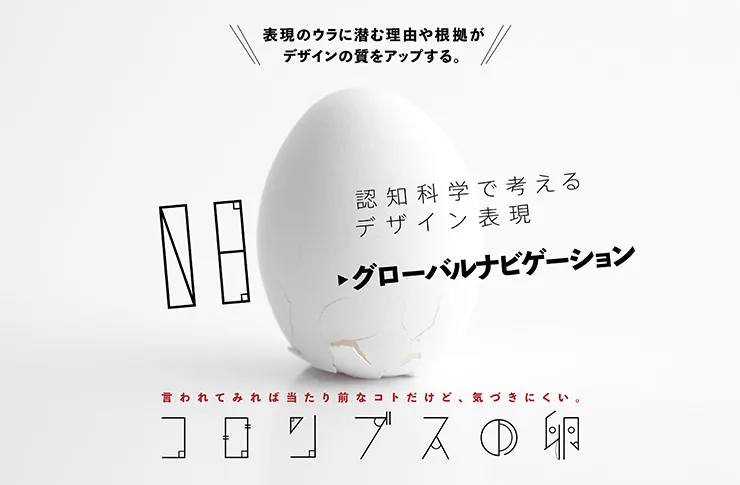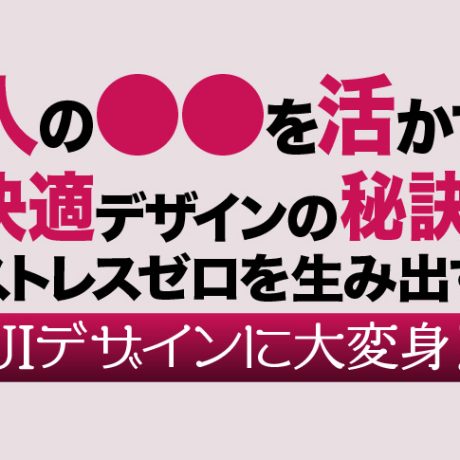複数の情報を順に覚える際、内容ではなく、
順番によって覚えやすさに違いが生じる。
複数の情報を順に覚えていく際、内容ではなく順番によって覚えやすさに違いが生じやすいという現象で、中間に覚える情報は忘れやすいのではなく、記憶に残りにくい傾向が強い。
ちなみに、無意味な文字列と意味のある文字列では、意味が通じる文字列の方が記憶に定着しやすい。
また、最初に覚えたことが記憶に残りやすい初頭効果や、最後に覚えたことが記憶に残りやすい新近効果の2つのしくみに影響を与えた。

具体例
- 結論を最初に述べて、理由を後に続けた上で最後に「まとめ」で情報をくり返す
- ランディングページや広告などで、特長やメリットなどをビジュアル的に最初に表示し、最後に背中を押す割引き情報や限定情報を表示する
- ナビゲーションメニューでは、利用者が多いコンテンツを先頭に配列し、最後にコミュニケーションに通じるメニューを配置する
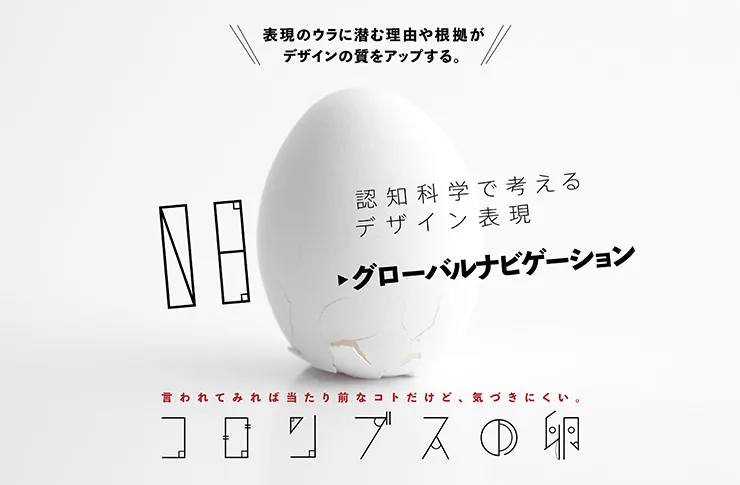
今回は、サイトを利用するすべてのユーザーの中でも、特に新規ユーザーに対して、わかりやすく行きたい情報へ直感的に遷移可能で、機動的な行動をサ...

特長や機能を知りたいユーザーに対して、どんな製品やサービスなのかを端的にイメージできて、印象に残りやすい特長一覧や機能一覧などのデザイン表現...
提唱者・発祥エピソード
19世紀に忘却曲線を発見したドイツの心理学者ヘルマン・エビングハウスが命名した「系列位置効果」は、のちに心理学者ソロモン・アッシュの「初頭効果(プライマシー効果)」や心理学者ノーマン・H・アンダーソンの「新近効果(リーセンシー効果)」の発見につながった。
参考文献・参考サイト
系列位置効果
https://uxdaystokyo.com/articles/glossary/serial-position-effect/
UX TIMES
系列位置効果
https://makitani.net/shimauma/serial-position-effect
シマウマ用語集
系列位置効果とは?
https://jetb.co.jp/12252
JetB
系列位置効果とは?論文や記憶との関連、日常例と実験法をわかりやすく解説
https://psycho-psycho.com/serial-position-effect/
Psycho Psycho
関連タグ
ナビゲーション@表現可能なデザインパーツ, ビジュアル@表現可能なデザインパーツ, リスト@表現可能なデザインパーツ, レイアウト@表現可能なデザインパーツ, ワーキングメモリ, 処理, 分析, 初頭効果, 新近効果, 短期記憶に関するミラーの法則, 記憶の多重貯蔵モデル, 記憶過程
このページと関係がある認知科学用語
-
記憶の多重貯蔵モデル記憶は、役割や機能の違いにより、視覚・聴覚などの五感から受けとる感覚記憶、情報を保管するだけでなく分析・処理する短期記憶、記憶と忘却の反復を経て数十年の単位で貯蔵される長期記憶と、3つの段階で構成されることで、人は非常に多く…
-
ワーキングメモリ感覚記憶から受けとった音声化できる情報は「音韻ループ」に、ビジュアルイメージは「視空間スケッチパッド」に一時的に保持し、長期記憶から「エピソードバッファ」に読み出された過去の経験や知識を「中央実行系」で解析・処理し、人が行動…
-
初頭効果(プライマシー効果)ものごとや人に対して最初に示された情報が、印象として記憶に残りやすく長期記憶にも引き継がれやすい、社会心理学における心理効果。 「リハーサル」と呼ばれる何度も繰り返し頭に思い浮かべる活動は、最初の方で得られる情報ほど何度も行…
-
新近効果(終末効果)複数の情報を与えられる際、最後に与えられた情報や直前に与えられた情報は、実際には大きな違いがないにも関わらず良い評価を得やすい傾向があり、「第一印象」よりも「最後の印象」の方が短期記憶に残りやすいため、印象に強い影響を持つ現…
-
短期記憶に関するミラーの法則(マジカルナンバー)数字や単語を記憶する場合、一般的な人の短期記憶(ワーキングメモリ)が保持できる15秒から30秒の間に、正しく覚えられる情報の量(チャンク)は7±2という法則。 チャンクとは、ひとつの意味や認識のかたまりを指し、記憶の限界数を…

![よくわかるUIデザイン講座 [ continue.jp ] よくわかるUIデザイン講座 [ continue.jp ]](https://continue.jp/wp-content/uploads/2022/11/rogoset.png?1766097386)