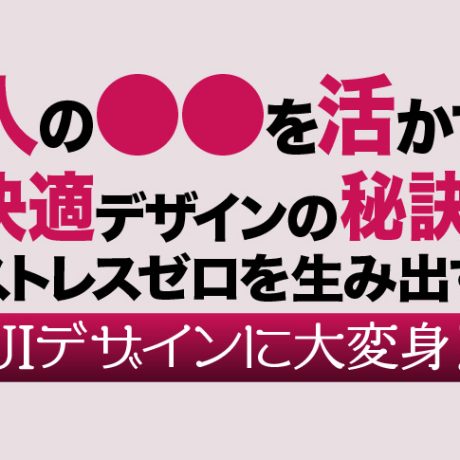記事目次
かんたんでわかりやすいまとまりで、
情報を認識する。
膨大な情報を処理する人の脳は、情報処理量を減らして効率化するために、無意識に情報を簡略化して認知する傾向がある。そのため、対象となる情報が複数ある場合、部分をひとつずつ認識するのではなく、全体をまとまりとして認識する。
これは、直感的で速い思考となる「システム1」に起因する。
端的な例でいうと、漢字は全体をまとまりとして理解しているため、構成する部分を一つひとつをずっと見続けていると、「こんなカタチだっけか!?」と不安になり、まとまりとして認知できなくなることがあるが、まとまりをイメージできなくなった状態を「ゲシュタルト崩壊」という。
まとまりに関する法則は、現在までに10以上が発見されている。
●近接
近くにあるもの同士は、まとまりとして認識されやすい。
●類同
カタチや色が似ているものは、まとまりとして認識されやすい。
●連続
交差する線など、連続する方向に繋がって認識されやすい。
●閉合
囲むように閉じた領域は、まとまりとして認識されやすい。
●共通運命
同じ方向に動くものや同じ周期で点滅するもの同士は、まとまりとして認識されやすい。
●面積
ふたつの図形が重なっているとき、面積の小さい方が主体(図)で大きい方が背景(地)として認識されやすい。
●対称性
左右対称のものは、まとまりとして認識されやすい。
などが挙げられる。
これらの中でも、複数の法則が重なって認められる場合は、より簡潔に認識できる方が優先される。
ちなみに、このプレグナンツの法則は、物事を部分的に捉えるのではなく、全体として捉える傾向があるという「ゲシュタルト心理学」の中心をなす概念。
「ゲシュタルト(Gestalt)は、ドイツ語で「形や形態」を意味し、心理学では、「部分同士が結びついた構成全体を捉えること」を表します。

表現可能なデザインパーツ
具体例
- 赤青緑の組み合わせは信号機として認識しているが、順番は覚えてない。
- 日の丸の国旗は、白い四角形に赤い丸が載っていて、四角形に丸い穴は空いていない。
- 縦につらない文章で、行間がおかしい時、タイトルが上に付くのか下に付くのかわからなくなる。
提唱者・発祥エピソード
ゲシュタルト心理学の創設者の一人であるチェコの心理学者マックス・ヴェルトハイマー氏によって、1923年「ゲシュタルト原則」の基礎となる6原則(近接・類同・連続・閉合・共通運命・良い形)が発表された。
「プレグナンツ」とは、日本語で「簡潔で意味のある」を意味するドイツ語。
参考文献・参考サイト
ゲシュタルトの法則とは? 資料作りの前にチェック!
STUDY HACKER
https://studyhacker.net/gestalt-law
ゲシュタルト原則(ゲシュタルトの法則)
UX TIMES
https://uxdaystokyo.com/articles/glossary/gestalt-principles/
プレグナンツの法則
UX TIMES
https://uxdaystokyo.com/articles/glossary/law-of-pragnanz/
心理学用語「プレグナンツの法則」とは?具体例から英語訳まで解説
スッキリ
https://gimon-sukkiri.jp/puregunantsunohousoku/
ゲシュタルト要因(プレグナンツの法則)とは? デザインを見やすくする7つの法則を活用しよう
LEARN TERN(ラン・タン)
https://learn-tern.com/gestalt/
![よくわかるUIデザイン講座 [ continue.jp ] よくわかるUIデザイン講座 [ continue.jp ]](https://continue.jp/wp-content/uploads/2022/11/rogoset.png?1768372159)